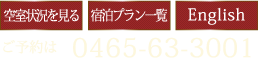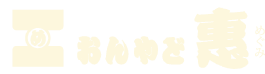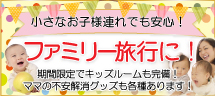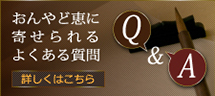小説 湯けむり

 この小説は、神奈川新聞に、昭和60年(1985年)11月17日から12月6日までの3週間に渡って、「神奈川人間紀行」の一部として連載されたものです。神奈川新聞社様のご厚意により、著作物転載の許可をいただき、公開しています。
この小説は、神奈川新聞に、昭和60年(1985年)11月17日から12月6日までの3週間に渡って、「神奈川人間紀行」の一部として連載されたものです。神奈川新聞社様のご厚意により、著作物転載の許可をいただき、公開しています。湯河原温泉「おんやど惠」の前身「惠旅館」、「惠ホテル」を舞台に、実話を基にした創作です。登場人物の大半は実在しますが、実名と仮名が混在しています。また、繰り広げられる逸話の数々も、大半は事実に基づいていますが、事実と異なる部分もあります。
あらすじ
かつての湯河原は温泉町というよりも湯治場として静かに湯けむりを立てていた。戦後間もなくの頃までは湯河原駅からいきなり湯治場が見えたというほど間には何もない田舎町だった。あちこちに湯けむりが立ち、いまのような温泉町に発展したのは戦後もしばらくたってからのことである。
恵ホテルの前身恵旅館も戦後に大きくなったそのうちの一軒だった。しかし、はじめは旅館といっても仕舞屋(しもたや)に二階を継ぎ足した粗末なつくり。しかも、銭湯の看板だけで旅館営業の許可はまだおりていないときだ。室伏あきが恵旅館へ来たのはその頃である。小田原の料理屋で女中をしていたあきは「臨時に」と頼まれてきて、そのまま旅館のおかみで居座ることになってしまった。亭主は仕事もやるかわり道楽も激しい。ほとんど家をあけたままで居たためしがない。あきはお産の産湯も自分で使えば、いかに女中を育てなじみ客をふやし旅館をにぎやかすかを女の細腕ひとつで奮闘してきた。自身もさのさや都々逸をこなす芸達者。女中から芸者から客までを巻き込んでの笑いと人情の人生譚をお届けする。
恵ホテルの前身恵旅館も戦後に大きくなったそのうちの一軒だった。しかし、はじめは旅館といっても仕舞屋(しもたや)に二階を継ぎ足した粗末なつくり。しかも、銭湯の看板だけで旅館営業の許可はまだおりていないときだ。室伏あきが恵旅館へ来たのはその頃である。小田原の料理屋で女中をしていたあきは「臨時に」と頼まれてきて、そのまま旅館のおかみで居座ることになってしまった。亭主は仕事もやるかわり道楽も激しい。ほとんど家をあけたままで居たためしがない。あきはお産の産湯も自分で使えば、いかに女中を育てなじみ客をふやし旅館をにぎやかすかを女の細腕ひとつで奮闘してきた。自身もさのさや都々逸をこなす芸達者。女中から芸者から客までを巻き込んでの笑いと人情の人生譚をお届けする。
第1話
戦後三年ほど経たお盆どきのことであった。小田原駅前の寿庵というそば屋に四人連れの客が入ってきた。
「お盆に予約もなしに箱根来るバカがあるかい」
「ここにいるじゃねえか」
「バカヤロ。今夜どこに泊まるんだよ」
「いまさらそんなこと言ったってしょうがねえじゃねえか。月日がさかのぼれるもんならちゃんと予約してきてやらあ」
言葉つきからいって土地の者ではなかった。さりとて勤め人にも見えない。職人で、それも仕事師といった感じの風態にみてとれた。
「オイ、そば屋さん」
仲間から盛んに罵られてきた幹事役らしい男が呼びかけた。
「ヘイ。なんでしょう」
そば屋が問い返した。
「どこでもいいんだけど、どっか温泉宿でひと晩ごやっかいになれるとこねえかい」
「ありますとも」
「オ、あるってよ」
その男は仲間を振り返った。箱根へ行って旅館をさんざん当たってどこもかしこも満員と断わられてきただけに、空いている温泉宿があると聞いてほっとした気持ちと不思議さがごっちゃになったような顔で言った。
「世間は広いようで狭いねえ。駄目だと思ってもやっぱり当たりはつけてみるもんだよ。ところでそば屋さん、いまじぶん行って泊まれるってえ宿屋はどこだい」
「湯河原です」
「オ。湯河原なら上等だ。なんて宿だい」
「恵旅館て、ちょうどウチと知り合いなんですけどいいところですよ」
「そうかい。じゃ、そこ行ってみよう」
四人連れは小気味よくそばをすすると礼を言って出て行った。
「お盆に予約もなしに箱根来るバカがあるかい」
「ここにいるじゃねえか」
「バカヤロ。今夜どこに泊まるんだよ」
「いまさらそんなこと言ったってしょうがねえじゃねえか。月日がさかのぼれるもんならちゃんと予約してきてやらあ」
言葉つきからいって土地の者ではなかった。さりとて勤め人にも見えない。職人で、それも仕事師といった感じの風態にみてとれた。
「オイ、そば屋さん」
仲間から盛んに罵られてきた幹事役らしい男が呼びかけた。
「ヘイ。なんでしょう」
そば屋が問い返した。
「どこでもいいんだけど、どっか温泉宿でひと晩ごやっかいになれるとこねえかい」
「ありますとも」
「オ、あるってよ」
その男は仲間を振り返った。箱根へ行って旅館をさんざん当たってどこもかしこも満員と断わられてきただけに、空いている温泉宿があると聞いてほっとした気持ちと不思議さがごっちゃになったような顔で言った。
「世間は広いようで狭いねえ。駄目だと思ってもやっぱり当たりはつけてみるもんだよ。ところでそば屋さん、いまじぶん行って泊まれるってえ宿屋はどこだい」
「湯河原です」
「オ。湯河原なら上等だ。なんて宿だい」
「恵旅館て、ちょうどウチと知り合いなんですけどいいところですよ」
「そうかい。じゃ、そこ行ってみよう」
四人連れは小気味よくそばをすすると礼を言って出て行った。
第2話
四人連れの男が湯河原駅に降り立つと番頭が出迎えに出ていた。
「小田原の寿庵さんからお越しになりました人たちですか」
「オウ、そうだい。よくわかるな」
「寿庵さんから電話を頂戴しましたので」
「ヘエ。そば屋にしちゃ気の利いた真似するじゃねえか」
駅からは相模の海が見え午後の陽に輝いて眠たくなるような気だるさを感じさせていた。右へ視線を振ると伊豆の山々が逆光にくすんでいた。そのふもとに湯治場の宿が点々として見えた。その湯治場と駅の間に田畑が横たわっていた。
「狐か狸が出てきそうなところだな。オイ、番頭さん、おめえ大丈夫かい」
「大丈夫ですよ」
「湯へ入ってるつもりがこえためだったなんてことにゃならねえだろうな」
「ご冗談を。狐が電話を受けるわけありません」
「そりゃそうだ」
へらず口を叩いているうちに一行は恵旅館に着いた。見れば仕舞屋に二階を継ぎ足した粗末な造りである。
「これが旅館かい。いよいよこえため風呂だよ」
番頭に案内されて四人連れが入って行くと玄関におかみが出迎えた。太り気味の体にがんもどきのような顔が乗っている。
「オイ、油揚げじゃねえ、ガンモドキが出て来たよ」
四人連れの中では一番若い三十五、六の男が仲間の袖を引いてプッと吹き出した。
「女中さんかい」
「いえ。わたしは恵旅館のおかみです。お見知りおきを願います」
それが室伏あきだった。
あきは四人連れを部屋へ案内すると宿帳を差し出した。
「アウ、タロ公、オメエ筆が立つだろ。代わりにみんなの名前書いとけや」
五十がらみの年輩の男がいちばん若い男に声をかけた。若い男は藤井某、橋場某、北見某と書いたあとで目時浅太郎と書いた。住所は川崎、横浜まちまちだった。あきは五十がらみの年輩の男を藤井、その藤井にタロ公と呼ばれた男を目時浅太郎と見当をつけた。
四人に着替えと風呂を勧めるとあきはいったん退がった。
「きたねえ部屋だなあ。なんてきたねえとこ世話しやがったんだ」
幹事役の北見がぼやいた。他の三人も呆れたり感心したりしている。
「まあ、いくらきたねえったってケツまで汚れやしねえだろ。ともあれひとっ風呂浴びようじゃねえか」
風呂へ行くとその風呂がまたきたなかった。
「そば屋のヤロー!」
そう言ったきり四人とも絶句してしまった。が、浴槽はきたないが湯だけは本物だった。
「まあいいや、一晩だけだ我慢しちゃおう」
湯の表面を這うように立ちのぼる湯気を見ているうちに、四人はようやくのことで温泉気分を取り戻してきた。
「小田原の寿庵さんからお越しになりました人たちですか」
「オウ、そうだい。よくわかるな」
「寿庵さんから電話を頂戴しましたので」
「ヘエ。そば屋にしちゃ気の利いた真似するじゃねえか」
駅からは相模の海が見え午後の陽に輝いて眠たくなるような気だるさを感じさせていた。右へ視線を振ると伊豆の山々が逆光にくすんでいた。そのふもとに湯治場の宿が点々として見えた。その湯治場と駅の間に田畑が横たわっていた。
「狐か狸が出てきそうなところだな。オイ、番頭さん、おめえ大丈夫かい」
「大丈夫ですよ」
「湯へ入ってるつもりがこえためだったなんてことにゃならねえだろうな」
「ご冗談を。狐が電話を受けるわけありません」
「そりゃそうだ」
へらず口を叩いているうちに一行は恵旅館に着いた。見れば仕舞屋に二階を継ぎ足した粗末な造りである。
「これが旅館かい。いよいよこえため風呂だよ」
番頭に案内されて四人連れが入って行くと玄関におかみが出迎えた。太り気味の体にがんもどきのような顔が乗っている。
「オイ、油揚げじゃねえ、ガンモドキが出て来たよ」
四人連れの中では一番若い三十五、六の男が仲間の袖を引いてプッと吹き出した。
「女中さんかい」
「いえ。わたしは恵旅館のおかみです。お見知りおきを願います」
それが室伏あきだった。
あきは四人連れを部屋へ案内すると宿帳を差し出した。
「アウ、タロ公、オメエ筆が立つだろ。代わりにみんなの名前書いとけや」
五十がらみの年輩の男がいちばん若い男に声をかけた。若い男は藤井某、橋場某、北見某と書いたあとで目時浅太郎と書いた。住所は川崎、横浜まちまちだった。あきは五十がらみの年輩の男を藤井、その藤井にタロ公と呼ばれた男を目時浅太郎と見当をつけた。
四人に着替えと風呂を勧めるとあきはいったん退がった。
「きたねえ部屋だなあ。なんてきたねえとこ世話しやがったんだ」
幹事役の北見がぼやいた。他の三人も呆れたり感心したりしている。
「まあ、いくらきたねえったってケツまで汚れやしねえだろ。ともあれひとっ風呂浴びようじゃねえか」
風呂へ行くとその風呂がまたきたなかった。
「そば屋のヤロー!」
そう言ったきり四人とも絶句してしまった。が、浴槽はきたないが湯だけは本物だった。
「まあいいや、一晩だけだ我慢しちゃおう」
湯の表面を這うように立ちのぼる湯気を見ているうちに、四人はようやくのことで温泉気分を取り戻してきた。
第3話
浅太郎たちが湯から上がって部屋へ戻ると熱いお茶に添えて茶菓子が山盛りになって出ていた。
「なんだいコリャ。ゼニふんだくられるんじゃねえだろうな」
「金のことなんか言うなよ。威勢が悪いじゃねえかよ」
そのうち夕食になって浅太郎たちはまたまた驚いた。煮しめの手料理に刺身がついてどぶろくまで出てきた。
昭和二十三年といえばまだ食糧事情の極めて悪い頃のことである。統制のもと刺身はおろか煮しめでさえ大ごちそうの時代であった。
「コノヤロ。コンチキショ。俺たちのこと見そこなってる。どっかのお大尽と間違えてやがんじゃねえのか」
「オイ。いよいよ狐タヌキだぜ。どぶろくの匂い嗅いでみろい」
浅太郎はどぶろくに鼻を近づけた。かつてない芳香である。少し飲んでみる。
「どうみたってコリャどぶろくだなあ。本物だ」
「そうか。エエ、こうなったらかまわねえ。飲んじゃえ。食っちゃえ。いくら狐だ狸だったって命までは取るめえ」
浅太郎たちにしてみれば狐や狸に化かされることよりも懐具合が心配だったのである。初めてのところで「もちっと安く」というのも体裁が悪いし、いざ勘定というときに「払いが足りない」とあっては男を下げる。そういう心配が先に立つほどのもてなしに合って、かえって腰が落ち着かなくなってしまった。
ひと晩明けてあくる朝、四人は目を覚ましてお互いの顔を見まわした。
「よかったなあ。野っぱらの真ん中じゃなくて」
「コレ見ろい」
藤井の言葉に浅太郎たちは目を向けた。藤井は手にアイロンのかかった開襟シャツを広げて持っていた。他の連中の開襟シャツも同様である。着たきりスズメのうすよごれたシャツがきれいに洗いあげられて糊までかかっていた。
「なかなか気が利いてんな、ここのウチの婆あのヤローなあ」
きれい好きの藤井はひとりで感心した。婆あといってもあきはまだ三十七だ。口の悪いはなしである。
藤井は早速あきを呼びつけた。
「バアさんね、オメエあんまり気が利くからね。こんどの正月にはたんとは連れてこられないけど二十人ぐらい仲間連れてきてやるからな」
勘定の心配などとうに忘れて先のことまで約束してしまった。
「そうですか。頼みますね。ところでご商売はなんですか」
礼を言うとあきはこうたずねた。
「バカヤロ。ご商売なんかあるかい横っトビだ」
「横っトビってなんですか」
「知らないのオバサン?」
からかわれているんだか真面目なんだか、あきはけげんな面持ちだった。が、横っトビが横浜の鳶職と知ってあきははじめて破顔一笑した。浅太郎たちもあきの持ってきた勘定書きを見てほっと胸をなでおろした。
思えば気を揉む長い一昼夜だった。
「なんだいコリャ。ゼニふんだくられるんじゃねえだろうな」
「金のことなんか言うなよ。威勢が悪いじゃねえかよ」
そのうち夕食になって浅太郎たちはまたまた驚いた。煮しめの手料理に刺身がついてどぶろくまで出てきた。
昭和二十三年といえばまだ食糧事情の極めて悪い頃のことである。統制のもと刺身はおろか煮しめでさえ大ごちそうの時代であった。
「コノヤロ。コンチキショ。俺たちのこと見そこなってる。どっかのお大尽と間違えてやがんじゃねえのか」
「オイ。いよいよ狐タヌキだぜ。どぶろくの匂い嗅いでみろい」
浅太郎はどぶろくに鼻を近づけた。かつてない芳香である。少し飲んでみる。
「どうみたってコリャどぶろくだなあ。本物だ」
「そうか。エエ、こうなったらかまわねえ。飲んじゃえ。食っちゃえ。いくら狐だ狸だったって命までは取るめえ」
浅太郎たちにしてみれば狐や狸に化かされることよりも懐具合が心配だったのである。初めてのところで「もちっと安く」というのも体裁が悪いし、いざ勘定というときに「払いが足りない」とあっては男を下げる。そういう心配が先に立つほどのもてなしに合って、かえって腰が落ち着かなくなってしまった。
ひと晩明けてあくる朝、四人は目を覚ましてお互いの顔を見まわした。
「よかったなあ。野っぱらの真ん中じゃなくて」
「コレ見ろい」
藤井の言葉に浅太郎たちは目を向けた。藤井は手にアイロンのかかった開襟シャツを広げて持っていた。他の連中の開襟シャツも同様である。着たきりスズメのうすよごれたシャツがきれいに洗いあげられて糊までかかっていた。
「なかなか気が利いてんな、ここのウチの婆あのヤローなあ」
きれい好きの藤井はひとりで感心した。婆あといってもあきはまだ三十七だ。口の悪いはなしである。
藤井は早速あきを呼びつけた。
「バアさんね、オメエあんまり気が利くからね。こんどの正月にはたんとは連れてこられないけど二十人ぐらい仲間連れてきてやるからな」
勘定の心配などとうに忘れて先のことまで約束してしまった。
「そうですか。頼みますね。ところでご商売はなんですか」
礼を言うとあきはこうたずねた。
「バカヤロ。ご商売なんかあるかい横っトビだ」
「横っトビってなんですか」
「知らないのオバサン?」
からかわれているんだか真面目なんだか、あきはけげんな面持ちだった。が、横っトビが横浜の鳶職と知ってあきははじめて破顔一笑した。浅太郎たちもあきの持ってきた勘定書きを見てほっと胸をなでおろした。
思えば気を揉む長い一昼夜だった。
第4話
室伏あきは明治四十三年小田原の在の寺町で生まれた。小さい頃から洋裁を習い、十五、六で女中奉公に出、恵旅館に来る前は関鳥という料理屋で女中をしていた。
恵旅館に来たといってもはじめは臨時の女中だった。恵旅館の上にままね館という湯治客相手の銭湯があって、そこだけでは湯治客をさばききれなくなって始めたのが恵旅館である。ままね館は湯治客を収容しきれなくなるとあぶれた客を馬車に乗せて恵旅館へまわして寄越した。
恵旅館という名は冠していても仕舞屋を改造しただけの建物である。湯もずっと上から引いてくるうちにぬるくなってしまっていた。しかも室伏良平のほか雇い人は臨時の女中で入ったあき一人。掃除、洗濯、めし炊き、料理、湯治客の世話と何がなんだかわからなくなってやっているうちに、いつしかあきは恵旅館のおかみになっていた。
あきが旅館のおかみに居直って、まず手こずったのが良平の頑固な性格だった。恵旅館は旅館業の届けをしていないために酒が出せない。なぜ旅館業の届けを出さなかったのかというと良平が大の酒嫌いだからだった。旅館の名を冠しておりながら旅館業の届けを怠ったのは良平が酒を出したくなかったからである。しかし、酒なくしてなんの旅館かなである。あきは良平を説得した。が、頑として応じない。
アーあ、えらい人と一緒になっちゃた。
気づいたが後悔先に立たずであった。臨時の女中で入ってから良平と所帯を持つにいたるまで、忙しすぎてあれこれ考えている間がなかったのである。
女中ならば自分が折れてそれですむ。が、おかみとなると将来のことを考えなければならない。良平がなんとしても説得に応じないとみてとると、あきは自分でどぶろくをつくりはじめた。違法だが背に腹はかえられなかった。
あきのつくるどぶろくは、樽を温泉につけておくために早く発酵した。それを押入れの床をくりぬいて土の中に埋めておくのである。その上にふとんやら枕やら雑多に積みあげておく。枕の中には米が入っていた。
税務署の役人が来てもわからない。
「その戸開けてください」
「ハイ、開けます」
役人に言われてあきが襖をあけるとただの押入れにしか見えない。
「ハイ、結構です」
税務署はひとつきに一度しか来ない。一度来ると一カ月は安心していられた。
あきが浅太郎たちに振る舞ったのは、こうしてつくったどぶろくである。狐の小便でも何でもない正真正銘のどぶろくだった。
しかし、税務署はだませたが、亭主の良平は収まらなかった。
「なんだ。また酒を出しやがったのか。いいかげんにしろ!」
当時はまだ泊まり客が少なかった。大半が近在の客で、湯に入ったあとで飲み食いして帰るだけ。酒を出す利もさほど大きくなかったのである。怒鳴られはしたが、怒っても税務署に通報しないのはさすがに夫婦だとあきは思った。
恵旅館に来たといってもはじめは臨時の女中だった。恵旅館の上にままね館という湯治客相手の銭湯があって、そこだけでは湯治客をさばききれなくなって始めたのが恵旅館である。ままね館は湯治客を収容しきれなくなるとあぶれた客を馬車に乗せて恵旅館へまわして寄越した。
恵旅館という名は冠していても仕舞屋を改造しただけの建物である。湯もずっと上から引いてくるうちにぬるくなってしまっていた。しかも室伏良平のほか雇い人は臨時の女中で入ったあき一人。掃除、洗濯、めし炊き、料理、湯治客の世話と何がなんだかわからなくなってやっているうちに、いつしかあきは恵旅館のおかみになっていた。
あきが旅館のおかみに居直って、まず手こずったのが良平の頑固な性格だった。恵旅館は旅館業の届けをしていないために酒が出せない。なぜ旅館業の届けを出さなかったのかというと良平が大の酒嫌いだからだった。旅館の名を冠しておりながら旅館業の届けを怠ったのは良平が酒を出したくなかったからである。しかし、酒なくしてなんの旅館かなである。あきは良平を説得した。が、頑として応じない。
アーあ、えらい人と一緒になっちゃた。
気づいたが後悔先に立たずであった。臨時の女中で入ってから良平と所帯を持つにいたるまで、忙しすぎてあれこれ考えている間がなかったのである。
女中ならば自分が折れてそれですむ。が、おかみとなると将来のことを考えなければならない。良平がなんとしても説得に応じないとみてとると、あきは自分でどぶろくをつくりはじめた。違法だが背に腹はかえられなかった。
あきのつくるどぶろくは、樽を温泉につけておくために早く発酵した。それを押入れの床をくりぬいて土の中に埋めておくのである。その上にふとんやら枕やら雑多に積みあげておく。枕の中には米が入っていた。
税務署の役人が来てもわからない。
「その戸開けてください」
「ハイ、開けます」
役人に言われてあきが襖をあけるとただの押入れにしか見えない。
「ハイ、結構です」
税務署はひとつきに一度しか来ない。一度来ると一カ月は安心していられた。
あきが浅太郎たちに振る舞ったのは、こうしてつくったどぶろくである。狐の小便でも何でもない正真正銘のどぶろくだった。
しかし、税務署はだませたが、亭主の良平は収まらなかった。
「なんだ。また酒を出しやがったのか。いいかげんにしろ!」
当時はまだ泊まり客が少なかった。大半が近在の客で、湯に入ったあとで飲み食いして帰るだけ。酒を出す利もさほど大きくなかったのである。怒鳴られはしたが、怒っても税務署に通報しないのはさすがに夫婦だとあきは思った。
第5話
室伏良平は親から恵旅館を任されはしたものの客商売はあまり好きではなかった。あきと一緒になったのも半ば自分の嫌うところを穴埋めして十分な働きに惚れたからだといってもよかった。
良平の目利き通り、おかみになってからのあきの働きにはめざましいものがあった。どぶろくづくりにとどまらない。裏の畑で野菜を作り、御殿場からの客には宿代がわりに米や野菜を持ってこさせ、あきはそれらの野菜で煮しめなどの手料理を作っては客に出して喜ばれた。旅館でありながら板前がいなかった。恵旅館にとってもあきの労だけで元手は要らず重宝したわけである。
冬場になると客の着る物に困った。当時のこととて丹前などという気の利いた代物はどこの旅館にもなかった。衣類を商う店でさえ置いてなかった代物だ。どうしてもとなれば小田原へ出て行けば買えたが、それだけの金がなかった。そこで、あきは自分が嫁入りに持ってきた銘仙などの地味な柄のものをほどいては洗い張りをし丹前に仕立て直した。
「あそこの家は丹前が出る」
恵旅館に客が来るようになったのは、口伝えにそんな評判が立ってからのことである。手が足りなくなるとあきは亭主に死なれて実家に帰っていた姉の山口かねを連れてきた。
良平にとってあきほど重宝な女房はなかった。商売の才覚を持った女を女房にするのも男の甲斐性のひとつと良平は自分で自分にうそぶいていたほどである。
湯河原にまだ芸者などいない時分に、あきは上客が来ると三味線を自ら弾いてさのさや都々逸を歌い踊った。関鳥で女中をしている時代、宮小路の芸者に手ほどきを受けたものである。
これは俺の出る幕ではないな。
良平はそう判断して、専ら外回りに徹することにした。朝一番の電車に乗って北関東から新潟まで足をのばし観光関係の会社をまわって客寄せをはじめた。帰りは夜の十時、十一時である。こうしていれば、客が飲む大嫌いな酒の匂いを嗅がずにすむこともあったが、働き者の女房を持って髪結いの亭主のようになることを嫌ったのが最大の理由であった。
夫婦でありながらほとんど顔を合わせることのない毎日が始まった。
「なにもそんなにまでして出かけることないのにさあ」
あきはそう説いたが、床の間の置物になりたくないという男の意地を通すところが良平の頑固といわれる頑固さのゆえんであった。
夫婦の努力があいまって客が来るようになるとこんどは熱い湯が欲しくなった。ままね館の温泉井戸も出が悪くなっていた。
「あんた、どうする? 温泉宿に温泉が来なくなっちまったらお手挙げだよ」
「そうだな。考えていたってしょうがねえ。出るか出ないか、ともあれテルさんに掘ってもらうべえよ」
テルさんというのは水道専門の工事屋である。温泉が出ても出なくても金を払うという約束で恵旅館の命運を賭けた井戸掘りが始まった。
良平の目利き通り、おかみになってからのあきの働きにはめざましいものがあった。どぶろくづくりにとどまらない。裏の畑で野菜を作り、御殿場からの客には宿代がわりに米や野菜を持ってこさせ、あきはそれらの野菜で煮しめなどの手料理を作っては客に出して喜ばれた。旅館でありながら板前がいなかった。恵旅館にとってもあきの労だけで元手は要らず重宝したわけである。
冬場になると客の着る物に困った。当時のこととて丹前などという気の利いた代物はどこの旅館にもなかった。衣類を商う店でさえ置いてなかった代物だ。どうしてもとなれば小田原へ出て行けば買えたが、それだけの金がなかった。そこで、あきは自分が嫁入りに持ってきた銘仙などの地味な柄のものをほどいては洗い張りをし丹前に仕立て直した。
「あそこの家は丹前が出る」
恵旅館に客が来るようになったのは、口伝えにそんな評判が立ってからのことである。手が足りなくなるとあきは亭主に死なれて実家に帰っていた姉の山口かねを連れてきた。
良平にとってあきほど重宝な女房はなかった。商売の才覚を持った女を女房にするのも男の甲斐性のひとつと良平は自分で自分にうそぶいていたほどである。
湯河原にまだ芸者などいない時分に、あきは上客が来ると三味線を自ら弾いてさのさや都々逸を歌い踊った。関鳥で女中をしている時代、宮小路の芸者に手ほどきを受けたものである。
これは俺の出る幕ではないな。
良平はそう判断して、専ら外回りに徹することにした。朝一番の電車に乗って北関東から新潟まで足をのばし観光関係の会社をまわって客寄せをはじめた。帰りは夜の十時、十一時である。こうしていれば、客が飲む大嫌いな酒の匂いを嗅がずにすむこともあったが、働き者の女房を持って髪結いの亭主のようになることを嫌ったのが最大の理由であった。
夫婦でありながらほとんど顔を合わせることのない毎日が始まった。
「なにもそんなにまでして出かけることないのにさあ」
あきはそう説いたが、床の間の置物になりたくないという男の意地を通すところが良平の頑固といわれる頑固さのゆえんであった。
夫婦の努力があいまって客が来るようになるとこんどは熱い湯が欲しくなった。ままね館の温泉井戸も出が悪くなっていた。
「あんた、どうする? 温泉宿に温泉が来なくなっちまったらお手挙げだよ」
「そうだな。考えていたってしょうがねえ。出るか出ないか、ともあれテルさんに掘ってもらうべえよ」
テルさんというのは水道専門の工事屋である。温泉が出ても出なくても金を払うという約束で恵旅館の命運を賭けた井戸掘りが始まった。
第6話
藤井や浅太郎があきに約束した通り二十人ほどの仕事師仲間を連れてやってきたのは、恵旅館が井戸掘り真最中の正月のことだった。
このときちょうど広間を仕切って小田原の漁師が芸者を挙げて宴会をやっていた。
こっちは泊まり、むこうは日帰りである。こちらがさあ始めようかというときにむこうは宴たけなわだった。
浅太郎たちの席にあいさつをすませてあきが出て来たところに男衆が駈け込んできた。
「おかみさん、大変だ。すぐ来てくれ」
大変だと聞いてあきは咄嗟に事故だと直観した。
「番頭さん、あと頼んだよ」と叫ぶとあきはもう外へとび出していた。あきは井戸掘りの現場に向かってあとも見ず夢中で走った。
その頃、宴会場ではちょっとしたもめごとが始まりかけていた。広川のカツと呼ばれる横浜の鳶が便所の帰りに隣の部屋へまぎれこんで芸者と踊りはじめたのである。
「あのバカ、どこの馬の骨だい」
「隣の部屋のヤツだろ。あきれ返ったヤツだぜ、まったく」
「ブン撲っちまおうか」
「よせよせ」と年輩の漁師は若い者を制しておいて広川のカツをたしなめた。「オイオイ、ニイサンよ。あんたの部屋は隣だよ。こんなところで油売ってないで自分の部屋に帰んなよ」
「こっちは好きで油売ってんだい。ほっといてくれ」
カエルの面に小便だった。
「ここはじきおひらきなんだからよ。帰ったがいいよ」
「おひらきならちょうどいいや。そんならこの芸者借りて行こう」
そう言って芸者を連れていこうと腕を引っぱったとたん広川のカツはそれまで腹に据えかねて見ていた若い漁師に思いきり頭をブン撲られた。
「なにしやがんだい、このスットコドッコイ」
「スットコドッコイはお前じゃねえか。小田原の漁師をなめんじゃねえぞ」
言い争っているところで広間を仕切っている襖がさっと開いた。横浜の鳶が二十人、ずらりと並んで立っている。
「カツ、おめえこんなとこで何やってやがんだ」
藤井が声をかけてきた。
「宴会が終わりだっていうから芸者を借りて行こうとしたらこん畜生がいきなり俺をブン撲ったんだ」
「あたりめえだ。あいさつもなしに、なめたまねしゃがるからだ」と漁師が吠えた。
「で、おめえ、撲られたまんまか」
「これから撲り返すとこだよ」
「よし、ヤレ。ごあいさつはそれからだ」
広川のカツは漁師をポカリとやった。鳶だの漁師だのと血の気の多い者同士である。取り合わせが悪かった。
「コノヤロー」
「コンチキショ!」
二十人の鳶と六十人の漁師がたちまちのうちに入り乱れた。
このときちょうど広間を仕切って小田原の漁師が芸者を挙げて宴会をやっていた。
こっちは泊まり、むこうは日帰りである。こちらがさあ始めようかというときにむこうは宴たけなわだった。
浅太郎たちの席にあいさつをすませてあきが出て来たところに男衆が駈け込んできた。
「おかみさん、大変だ。すぐ来てくれ」
大変だと聞いてあきは咄嗟に事故だと直観した。
「番頭さん、あと頼んだよ」と叫ぶとあきはもう外へとび出していた。あきは井戸掘りの現場に向かってあとも見ず夢中で走った。
その頃、宴会場ではちょっとしたもめごとが始まりかけていた。広川のカツと呼ばれる横浜の鳶が便所の帰りに隣の部屋へまぎれこんで芸者と踊りはじめたのである。
「あのバカ、どこの馬の骨だい」
「隣の部屋のヤツだろ。あきれ返ったヤツだぜ、まったく」
「ブン撲っちまおうか」
「よせよせ」と年輩の漁師は若い者を制しておいて広川のカツをたしなめた。「オイオイ、ニイサンよ。あんたの部屋は隣だよ。こんなところで油売ってないで自分の部屋に帰んなよ」
「こっちは好きで油売ってんだい。ほっといてくれ」
カエルの面に小便だった。
「ここはじきおひらきなんだからよ。帰ったがいいよ」
「おひらきならちょうどいいや。そんならこの芸者借りて行こう」
そう言って芸者を連れていこうと腕を引っぱったとたん広川のカツはそれまで腹に据えかねて見ていた若い漁師に思いきり頭をブン撲られた。
「なにしやがんだい、このスットコドッコイ」
「スットコドッコイはお前じゃねえか。小田原の漁師をなめんじゃねえぞ」
言い争っているところで広間を仕切っている襖がさっと開いた。横浜の鳶が二十人、ずらりと並んで立っている。
「カツ、おめえこんなとこで何やってやがんだ」
藤井が声をかけてきた。
「宴会が終わりだっていうから芸者を借りて行こうとしたらこん畜生がいきなり俺をブン撲ったんだ」
「あたりめえだ。あいさつもなしに、なめたまねしゃがるからだ」と漁師が吠えた。
「で、おめえ、撲られたまんまか」
「これから撲り返すとこだよ」
「よし、ヤレ。ごあいさつはそれからだ」
広川のカツは漁師をポカリとやった。鳶だの漁師だのと血の気の多い者同士である。取り合わせが悪かった。
「コノヤロー」
「コンチキショ!」
二十人の鳶と六十人の漁師がたちまちのうちに入り乱れた。
第7話
茶碗ごとめしは飛んでくる膳はひっくり返るで刺身も煮しめも見分けがつかないほど踏んずけられて畳にこびりついてしまった。部屋の外に逃れひっくり返ってうんうん唸っているのもいれば着ているものにおかずとごはんをベットリつけて取っ組み合っているのもいた。みんな血だらけである。真っ蒼な顔でかけつけた番頭まで階段の下へ投げ落とされる仕末。打ちどころが悪かったのか番頭はのびて動かなくなってしまった。
「オイ、番頭死んじまったんじゃねえか。動かねえぞ!」
だれかが抑えたような声で叫んだ。その言葉が修羅場にいいようのない衝撃を与えた。エンストを起こした車のように罵声も品物の壊れる音もたちまちやんでしまった。
「オイ!ほんとか!」
敵味方も忘れて顔を見つめあった。もともと面白半分に始めた喧嘩だ。多少の怪我はともかく死人までは計算に入れていなかった。われに返ってまわりを見まわしてあまりの惨状に二度驚いた。
そんなこととも知らず、井戸掘りの現場であきはピンコロとび跳ねていた。熱い良質の温泉を掘り当てたのである。
「出た、出た、出た、出た!」
あきは一目散にもと来た道を駈けだした。
広間では、息を吹き返した番頭が仁王立ちでしゅんとなった鳶と漁師に小言を並べ立てていた。
「出た、出た、出たよお!」
そこへあきがとびこんできた。その場の惨状を見て喜色満面のあきの顔は一瞬ポカンとした表情に変わった。当然である。
「おかみさん、見てくださいよ、コレ。わたしは警察へ訴えてきます」
「ちょい待ち番頭さん」。行きかける番頭をあきは引きとめた。「ウチで起きたことを警察へなんか届けてどうすんだい。ウチで起きたことはウチでおさめるから余計なことしないでちょうだい」
あきの意外な言葉に、番頭はじめ鳶も漁師もみんな呆気にとられた。
「仲直りする前に、みなさんすみませんが風呂入って汚れ落としてきてください」
いわれるまま鳶も漁師も肩を落として悄然と出て行った。喧嘩前の威勢がウソのようである。
風呂から上がってくると浴衣は全部新しいのと替えてあった。広間へ戻るとお膳がズラッと新しく出し直してある。
「エライ婆あだよ。コリャ、ゼニいくらふんだくられるかわかったもんじゃないぞ」
戦々兢々としながら「本日の損害は鳶が七で漁師が三の割合でもつ」ことで手打ちをすませた。ところがあきはそれに取り合わない。
「きょうのこの席は金なんか取らない」
取らないどころか自分から三味線を取ってさのさだ都々逸だとドンチャン騒ぎの音頭を取り始めた。
「気に入った。来年は六十人から仲間をふやして連れてくるからな」
藤井はそういって膝を叩いた。
温泉は湧く、客には惚れられる。あきはがんもどきのような顔を紅潮させピンコロ跳ねて踊った。
「オイ、番頭死んじまったんじゃねえか。動かねえぞ!」
だれかが抑えたような声で叫んだ。その言葉が修羅場にいいようのない衝撃を与えた。エンストを起こした車のように罵声も品物の壊れる音もたちまちやんでしまった。
「オイ!ほんとか!」
敵味方も忘れて顔を見つめあった。もともと面白半分に始めた喧嘩だ。多少の怪我はともかく死人までは計算に入れていなかった。われに返ってまわりを見まわしてあまりの惨状に二度驚いた。
そんなこととも知らず、井戸掘りの現場であきはピンコロとび跳ねていた。熱い良質の温泉を掘り当てたのである。
「出た、出た、出た、出た!」
あきは一目散にもと来た道を駈けだした。
広間では、息を吹き返した番頭が仁王立ちでしゅんとなった鳶と漁師に小言を並べ立てていた。
「出た、出た、出たよお!」
そこへあきがとびこんできた。その場の惨状を見て喜色満面のあきの顔は一瞬ポカンとした表情に変わった。当然である。
「おかみさん、見てくださいよ、コレ。わたしは警察へ訴えてきます」
「ちょい待ち番頭さん」。行きかける番頭をあきは引きとめた。「ウチで起きたことを警察へなんか届けてどうすんだい。ウチで起きたことはウチでおさめるから余計なことしないでちょうだい」
あきの意外な言葉に、番頭はじめ鳶も漁師もみんな呆気にとられた。
「仲直りする前に、みなさんすみませんが風呂入って汚れ落としてきてください」
いわれるまま鳶も漁師も肩を落として悄然と出て行った。喧嘩前の威勢がウソのようである。
風呂から上がってくると浴衣は全部新しいのと替えてあった。広間へ戻るとお膳がズラッと新しく出し直してある。
「エライ婆あだよ。コリャ、ゼニいくらふんだくられるかわかったもんじゃないぞ」
戦々兢々としながら「本日の損害は鳶が七で漁師が三の割合でもつ」ことで手打ちをすませた。ところがあきはそれに取り合わない。
「きょうのこの席は金なんか取らない」
取らないどころか自分から三味線を取ってさのさだ都々逸だとドンチャン騒ぎの音頭を取り始めた。
「気に入った。来年は六十人から仲間をふやして連れてくるからな」
藤井はそういって膝を叩いた。
温泉は湧く、客には惚れられる。あきはがんもどきのような顔を紅潮させピンコロ跳ねて踊った。
第8話
木内久子があきにスカウトされたのはこの頃のことであった。鳶だテキ屋だと団体客がたてこんでくるとよく働く女中がなんとしても必要になってきた。
久子は毎日毎日狭霧の立つ千歳川で洗濯をしていた。このときまだ十九歳。嫁に行ったが逃げ戻って韮山の実家から縁戚にあたる松井という電気屋に預けられていたのである。洗濯の手を休めると過ぎ去った日のことが脳裡に浮かんでくるので久子は洗濯の手を休めず一心に洗い続けた。その働きぶりがあきの目にとまったのである。
久子の家は当時としては大百姓の部類に属した。父親は二十六のときから村会議員をやり村の政治にかかわってきた。そんな関係で一年三百六十五日久子の家には来客の絶えたためしがない。久子の母はその客をもてなすどぶろくつくりに追われていた。結婚式やら何やら近所で祝い事があると、久子の母は二十畳敷もある板の間の縁下からどぶろくを絞りあげては一升びんに詰め、十本、二十本と届けていた。幼い頃の久子は、いつもあかい色をした母の顔を不思議に思ってみつめたものである。
雨が降ると手の甲大の沢ガニが近くの川に流されて下ってきた。それを竹編みの大きなカゴに取ってきては甲らをあけ足を取ってカニ汁をつくるのが久子の腕自慢だった。大根、ニンジン、ゴボウなどと一緒に沢ガニを大きな鉄ナベで煮るのである。
「久子ちゃんの作るカニ汁は最高だ」
千歳川の流れを見ていると韮山の川が思い出された。思い出すまいと思ってもつい手の動きがのろくなって韮山のことを想い浮かべた。ハッとして気がつくと久子はまたせっせと洗濯物をもみはじめた。
その韮山から伊豆長岡へ久子が嫁に行ったのは十九のときである。いちばん上の姉はすでに大百姓の跡取り息子のところへ嫁ぎ、その下の姉も沼津の水産加工屋へ嫁に行っていた。順繰りで久子も見合いさせられた。ちょうどそのとき好きな恋人のいた久子は相手の顔も見なかった。
が、久子は父親にいやと言えなかった。頑固な父親に服従することに慣らされてしまっていたからである。
当時としては珍しいミシンやらたくさんの嫁入道具を馬力に積んで韮山から伊豆長岡へ久子は嫁入りして行った。その嫁入先から久子はわずか一カ月半で韮山に逃げ帰ってきてしまった。
おお嫌だ嫌だ。
久子は思わず洗濯物を千歳川の水でバシャバシャすすいだ。洗濯物にまで自分の忌わしい過去がしみついているかのように。
「あの娘(こ)洗濯ばっかしてるけどよお。弁慶縞の帯なんか締めてあんなところで洗濯してるような娘じゃないよお」
「親類から預かってるだもの仕方ねえよ」
「ウチへ少し寄越しなよ。悪いようにはしねえだからよ」
「親がいけねえっていうよ」
「親が来たら寄越しとくれよ。ウチで話をするだからよ」
あきは松井の奥さんを口説きはじめた。
久子は毎日毎日狭霧の立つ千歳川で洗濯をしていた。このときまだ十九歳。嫁に行ったが逃げ戻って韮山の実家から縁戚にあたる松井という電気屋に預けられていたのである。洗濯の手を休めると過ぎ去った日のことが脳裡に浮かんでくるので久子は洗濯の手を休めず一心に洗い続けた。その働きぶりがあきの目にとまったのである。
久子の家は当時としては大百姓の部類に属した。父親は二十六のときから村会議員をやり村の政治にかかわってきた。そんな関係で一年三百六十五日久子の家には来客の絶えたためしがない。久子の母はその客をもてなすどぶろくつくりに追われていた。結婚式やら何やら近所で祝い事があると、久子の母は二十畳敷もある板の間の縁下からどぶろくを絞りあげては一升びんに詰め、十本、二十本と届けていた。幼い頃の久子は、いつもあかい色をした母の顔を不思議に思ってみつめたものである。
雨が降ると手の甲大の沢ガニが近くの川に流されて下ってきた。それを竹編みの大きなカゴに取ってきては甲らをあけ足を取ってカニ汁をつくるのが久子の腕自慢だった。大根、ニンジン、ゴボウなどと一緒に沢ガニを大きな鉄ナベで煮るのである。
「久子ちゃんの作るカニ汁は最高だ」
千歳川の流れを見ていると韮山の川が思い出された。思い出すまいと思ってもつい手の動きがのろくなって韮山のことを想い浮かべた。ハッとして気がつくと久子はまたせっせと洗濯物をもみはじめた。
その韮山から伊豆長岡へ久子が嫁に行ったのは十九のときである。いちばん上の姉はすでに大百姓の跡取り息子のところへ嫁ぎ、その下の姉も沼津の水産加工屋へ嫁に行っていた。順繰りで久子も見合いさせられた。ちょうどそのとき好きな恋人のいた久子は相手の顔も見なかった。
が、久子は父親にいやと言えなかった。頑固な父親に服従することに慣らされてしまっていたからである。
当時としては珍しいミシンやらたくさんの嫁入道具を馬力に積んで韮山から伊豆長岡へ久子は嫁入りして行った。その嫁入先から久子はわずか一カ月半で韮山に逃げ帰ってきてしまった。
おお嫌だ嫌だ。
久子は思わず洗濯物を千歳川の水でバシャバシャすすいだ。洗濯物にまで自分の忌わしい過去がしみついているかのように。
「あの娘(こ)洗濯ばっかしてるけどよお。弁慶縞の帯なんか締めてあんなところで洗濯してるような娘じゃないよお」
「親類から預かってるだもの仕方ねえよ」
「ウチへ少し寄越しなよ。悪いようにはしねえだからよ」
「親がいけねえっていうよ」
「親が来たら寄越しとくれよ。ウチで話をするだからよ」
あきは松井の奥さんを口説きはじめた。
第9話
親の一存で進められた見合いと結婚それに続く離婚で久子は生活の根っこをなくして宙ぶらりんな気持ちになっていた。いままで順調に捗ってきた人生の歩みが突如中断したような虚無感が胸のうちにあった。
そんなときに松井の叔母からあきのたっての頼みを聞かされて久子は行ってみようという気になった。決めると久子はすぐにその足であきをたずねた。
恵旅館にはすでにノンちゃん、ユキちゃん、サッちゃんなどの学校出たての女中っこがいてあきの子どもの子守りをしていた。妹のいない久子にはそれがうれしかった。久子は恵旅館へ来てからは千恵という名をもらいチーちゃんと呼ばれるようになった。
数日後、久子の父親が現れた。
「ヨオ。ウチの久子いますか」
頑固で几帳面でお役人然とした紳士だった。それがのっけから切口上である。
「いません」
あきはソラをつかった。
「そんなことねえ。この間松井のところから来たはずだ」
「来てはいます。でも、いまはいません」
「どこ行った」
「さあ」
あきは部屋中を探したが久子の姿はなかった。探しまわるあきの袖を姉のかねが引いて言った。
「チーちゃんはいま洋服タンスの中にいるだからよ。オジンが行っちゃったら出すだからな。駄目だよ、いま言っちゃ」
久子は洋服タンスの中で息をひそめていた。そうしてるうちに何がなんでもここにいなければという気になってきた。必死に息を殺していると外から扉が開いた。
「行っちゃっただよ、チーちゃん」
久子はタンスから出るとその場にへたりこんで安堵の胸をなでおろした。
「オジンが迎えに来ちゃったけど、どうする?」
「どうするって……」
久子は返答に窮した。
「かたちだけでもいっぺん帰りなよ。松井さんの立場もあるだし」
あきに説得されて久子はいったん韮山の実家へ帰った。帰るなり久子は父親に向かって宣言した。
「あたし恵旅館で女中をやります」
父親のいいなりで嫁に行って失敗したからこんどは自分の意志でしっかり生きようと久子は心に決めていた。
久子の父親は烈火のごとく怒った。
「木内の家から旅館の女中なんぞ出せるか!」
「それはおとうさんの勝手です。あたしは行きます」
久子は頬にビンタが飛んだ。不思議なことにビンタを一発くったあとはもう何もこわくなくなった。かえって肚が座った。
「おまえは木内のツラ汚しだ。もしどうしてもというんなら異動証明持ってけ」
「はい」
ふたたび久子の頬にビンタが飛んだ。ぶたれているうちにビンタはゲンコツに変わった。
そんなときに松井の叔母からあきのたっての頼みを聞かされて久子は行ってみようという気になった。決めると久子はすぐにその足であきをたずねた。
恵旅館にはすでにノンちゃん、ユキちゃん、サッちゃんなどの学校出たての女中っこがいてあきの子どもの子守りをしていた。妹のいない久子にはそれがうれしかった。久子は恵旅館へ来てからは千恵という名をもらいチーちゃんと呼ばれるようになった。
数日後、久子の父親が現れた。
「ヨオ。ウチの久子いますか」
頑固で几帳面でお役人然とした紳士だった。それがのっけから切口上である。
「いません」
あきはソラをつかった。
「そんなことねえ。この間松井のところから来たはずだ」
「来てはいます。でも、いまはいません」
「どこ行った」
「さあ」
あきは部屋中を探したが久子の姿はなかった。探しまわるあきの袖を姉のかねが引いて言った。
「チーちゃんはいま洋服タンスの中にいるだからよ。オジンが行っちゃったら出すだからな。駄目だよ、いま言っちゃ」
久子は洋服タンスの中で息をひそめていた。そうしてるうちに何がなんでもここにいなければという気になってきた。必死に息を殺していると外から扉が開いた。
「行っちゃっただよ、チーちゃん」
久子はタンスから出るとその場にへたりこんで安堵の胸をなでおろした。
「オジンが迎えに来ちゃったけど、どうする?」
「どうするって……」
久子は返答に窮した。
「かたちだけでもいっぺん帰りなよ。松井さんの立場もあるだし」
あきに説得されて久子はいったん韮山の実家へ帰った。帰るなり久子は父親に向かって宣言した。
「あたし恵旅館で女中をやります」
父親のいいなりで嫁に行って失敗したからこんどは自分の意志でしっかり生きようと久子は心に決めていた。
久子の父親は烈火のごとく怒った。
「木内の家から旅館の女中なんぞ出せるか!」
「それはおとうさんの勝手です。あたしは行きます」
久子は頬にビンタが飛んだ。不思議なことにビンタを一発くったあとはもう何もこわくなくなった。かえって肚が座った。
「おまえは木内のツラ汚しだ。もしどうしてもというんなら異動証明持ってけ」
「はい」
ふたたび久子の頬にビンタが飛んだ。ぶたれているうちにビンタはゲンコツに変わった。
第10話
二日ほどして顔中に青アザをこしらえた久子が恵旅館の玄関に立った。
「まあ」
あきは言葉もない。
「あたし韮山の家には絶対帰りません。よろしくおねがいします」
久子はぴょこんとおじぎをした。
その久子のあとを追うようにして父親がやって来た。
「どうなんだ。まだ考えは変わらねえだか?」
「変わりません」
久子はいっこく者の父親に向かってきっぱりと言い放った。
「そうか。じゃおまえはもう家へ帰っちゃいけねえよ。異動証明こっちへ送る手続きを取っただからな」
このうえないという仏頂面で父親はあきのほうに向き直った。
「じゃおたくにやりますからね。いいですね」
「いいですよ。どうぞもうお帰りください」
あきはゴーホームといわんばかりに玄関の外を指差した。玄関先で立ったままの応待である。ひどく礼を失したやり方だと思ったが、なまじ取りなして話がこんがらがってもいけない。久子にも父親にも悪い気がしたがあきはすげなく追い返すような態度を取り通した。案の定父親はかんかんに怒って帰って行った。
数日後、久子の異動証明が本当に送りつけられてきた。久子の運命は決まった。
チーちゃんこと久子は自分の意志で恵旅館へ来たが、ノンちゃん、ユキちゃん、サッちゃんといった女中っ子は、あきが学校へ頼み込んで連れてきた子どもたちである。いずれも親の意志で寄越されてきていた。
ある日のこと。あきが温泉場の道を歩いていると見かけない男が立ち話をしていた。
「どうだうまくいったか」
「いった」
短い会話だがあきにはピンときた。旅館にとんで帰るとノンちゃんがいない。あきはあとを追った。道々人に聞くと駅へ向かって歩くノンちゃんを見かけたという。駅員に聞くと「つい先程上りに乗った」と教えてくれた。
あきの予感は当たった。ノンちゃんは引き抜きに合ったのだ。立ち話をしていたのは働き者の女中っ子を引き抜きに来ていた男たちであった。
あきはノンちゃんの行き先をとりあえず小田原と踏んだ。小田原で列車を降りて駅前へ出てくるとノンちゃんが真新しい駒下駄を大事そうに抱えて立っていた。あとから来る引き抜きの男たちを待っていたらしい。
「ノンちゃん、こんなところで何やってんだい」
「アーおかみさん」
ノンちゃんは驚いて目を見張った
「こんな下駄ひとつでつられちゃ駄目だよ。ウチで辛抱すればもっといいもん買ってやれるだに」
ユキちゃんがいなくなったときは秦野の家まで探しに行った。女中が居つくようでなければ旅館ははやらない。あきは必死だった。
が、サッちゃんだけは進駐軍のオンリーのほうが金になると言って親が連れて行った。親の意志では引きとめられなかった。それがあきの大きな悔いになっている。
「まあ」
あきは言葉もない。
「あたし韮山の家には絶対帰りません。よろしくおねがいします」
久子はぴょこんとおじぎをした。
その久子のあとを追うようにして父親がやって来た。
「どうなんだ。まだ考えは変わらねえだか?」
「変わりません」
久子はいっこく者の父親に向かってきっぱりと言い放った。
「そうか。じゃおまえはもう家へ帰っちゃいけねえよ。異動証明こっちへ送る手続きを取っただからな」
このうえないという仏頂面で父親はあきのほうに向き直った。
「じゃおたくにやりますからね。いいですね」
「いいですよ。どうぞもうお帰りください」
あきはゴーホームといわんばかりに玄関の外を指差した。玄関先で立ったままの応待である。ひどく礼を失したやり方だと思ったが、なまじ取りなして話がこんがらがってもいけない。久子にも父親にも悪い気がしたがあきはすげなく追い返すような態度を取り通した。案の定父親はかんかんに怒って帰って行った。
数日後、久子の異動証明が本当に送りつけられてきた。久子の運命は決まった。
チーちゃんこと久子は自分の意志で恵旅館へ来たが、ノンちゃん、ユキちゃん、サッちゃんといった女中っ子は、あきが学校へ頼み込んで連れてきた子どもたちである。いずれも親の意志で寄越されてきていた。
ある日のこと。あきが温泉場の道を歩いていると見かけない男が立ち話をしていた。
「どうだうまくいったか」
「いった」
短い会話だがあきにはピンときた。旅館にとんで帰るとノンちゃんがいない。あきはあとを追った。道々人に聞くと駅へ向かって歩くノンちゃんを見かけたという。駅員に聞くと「つい先程上りに乗った」と教えてくれた。
あきの予感は当たった。ノンちゃんは引き抜きに合ったのだ。立ち話をしていたのは働き者の女中っ子を引き抜きに来ていた男たちであった。
あきはノンちゃんの行き先をとりあえず小田原と踏んだ。小田原で列車を降りて駅前へ出てくるとノンちゃんが真新しい駒下駄を大事そうに抱えて立っていた。あとから来る引き抜きの男たちを待っていたらしい。
「ノンちゃん、こんなところで何やってんだい」
「アーおかみさん」
ノンちゃんは驚いて目を見張った
「こんな下駄ひとつでつられちゃ駄目だよ。ウチで辛抱すればもっといいもん買ってやれるだに」
ユキちゃんがいなくなったときは秦野の家まで探しに行った。女中が居つくようでなければ旅館ははやらない。あきは必死だった。
が、サッちゃんだけは進駐軍のオンリーのほうが金になると言って親が連れて行った。親の意志では引きとめられなかった。それがあきの大きな悔いになっている。
第11話
客がふえるにつれて久子たちはふとんつくりに追われた。新しくつくるだけでなく、古くなって汚れたふとんは洗って干して中身を入れ替えた。夏の暑いさなか、汗みどろになって綿ぼこりにまみれて働いた。
「終わったらキネマ連れてってやるからね」
暑さと汗と疲れでダレそうになるとあきがやってきてそう言った。あきは決して「働け」という言い方はしなかった。ノンちゃんもユキちゃんもそのひとことで気を取り直した。
湯河原にはキネマという名の映画館が一軒だけあった。そこで映画を見て帰りにラーメンを食べるのがあきのごほうびだった。その頃はラーメンを取り寄せて食べることなど考えられなかった。映画とそのラーメン一杯がうれしくてみんな夢中で働いたのである。
夜、女中部屋に帰って寝る前に久子たちはあきの部屋へいって膝を折り「おかみさん、おやすみなさい」とあいさつしてから眠りにつく習慣になっていた。
ソフトクリームの出始めの頃である。久子たちはあきにあいさつをすませると窓からぬけ出してソフトクリームを食べに行った。もぬけのからになった女中部屋へあきが心配してのぞきに来た。
望みをとげて久子たちが窓から入ってくるとあきが部屋の中に座っていた。
「三人ともそこに座りなさい」
「すみません」
久子、ノンちゃん、ユキちゃんと三人の女中は肩をすぼめると一列になってあきの前に座った。
「謝る前に聞きなさいよ。窓から出入りするなんて娘っ子のすることだかね。まして夜道を娘っ子だけで歩くなんて、万一のことがあったらどうするだね」
「すみませーん」
三人は揃って頭を下げた。
こってり油を絞られた翌日は、三人は決まって一日中口をきかなくなった。忙しすぎる。少しぐらい自分たちで遊んで歩く時間があったっていいだよ。そんな気持ちがだれの胸にもあったからである。
その晩あきのところへ就寝前のあいさつに行くと「これお食べ」と言うとあきは菓子の包みを差し出した。それでノンちゃんやユキちゃんの気嫌はたちまち直った。
たあいないといえばいえる。久子にはそんな二人が妹のようにも想え、あきは母親のように感じられた。恵旅館の面々は家を失った久子にとっては新しい家族だった。
が、ここは父親のいない家族だった。良平は青ペン、赤ペン、白ペンなどと呼ばれる赤線に〈恵〉というパンパン屋を出していて、〈恵〉の女を連れては熱海へダンスをしに通っていた。朝五時に出て夜の十時まで客取りに各地をまわってきたあと遊びに出るのである。ときには最終列車の行ったあと線路伝いに熱海まで歩いて遊びに行くこともあった。こんなときはむろん一人だった。良平のダンス上手のダンス好きは姿に似ず定評があった。
「ここのウチは旦那がいねえのかい」
なじみ客さえそう言って首をかしげた。良平の酒嫌いも相変わらずだったのである。
「終わったらキネマ連れてってやるからね」
暑さと汗と疲れでダレそうになるとあきがやってきてそう言った。あきは決して「働け」という言い方はしなかった。ノンちゃんもユキちゃんもそのひとことで気を取り直した。
湯河原にはキネマという名の映画館が一軒だけあった。そこで映画を見て帰りにラーメンを食べるのがあきのごほうびだった。その頃はラーメンを取り寄せて食べることなど考えられなかった。映画とそのラーメン一杯がうれしくてみんな夢中で働いたのである。
夜、女中部屋に帰って寝る前に久子たちはあきの部屋へいって膝を折り「おかみさん、おやすみなさい」とあいさつしてから眠りにつく習慣になっていた。
ソフトクリームの出始めの頃である。久子たちはあきにあいさつをすませると窓からぬけ出してソフトクリームを食べに行った。もぬけのからになった女中部屋へあきが心配してのぞきに来た。
望みをとげて久子たちが窓から入ってくるとあきが部屋の中に座っていた。
「三人ともそこに座りなさい」
「すみません」
久子、ノンちゃん、ユキちゃんと三人の女中は肩をすぼめると一列になってあきの前に座った。
「謝る前に聞きなさいよ。窓から出入りするなんて娘っ子のすることだかね。まして夜道を娘っ子だけで歩くなんて、万一のことがあったらどうするだね」
「すみませーん」
三人は揃って頭を下げた。
こってり油を絞られた翌日は、三人は決まって一日中口をきかなくなった。忙しすぎる。少しぐらい自分たちで遊んで歩く時間があったっていいだよ。そんな気持ちがだれの胸にもあったからである。
その晩あきのところへ就寝前のあいさつに行くと「これお食べ」と言うとあきは菓子の包みを差し出した。それでノンちゃんやユキちゃんの気嫌はたちまち直った。
たあいないといえばいえる。久子にはそんな二人が妹のようにも想え、あきは母親のように感じられた。恵旅館の面々は家を失った久子にとっては新しい家族だった。
が、ここは父親のいない家族だった。良平は青ペン、赤ペン、白ペンなどと呼ばれる赤線に〈恵〉というパンパン屋を出していて、〈恵〉の女を連れては熱海へダンスをしに通っていた。朝五時に出て夜の十時まで客取りに各地をまわってきたあと遊びに出るのである。ときには最終列車の行ったあと線路伝いに熱海まで歩いて遊びに行くこともあった。こんなときはむろん一人だった。良平のダンス上手のダンス好きは姿に似ず定評があった。
「ここのウチは旦那がいねえのかい」
なじみ客さえそう言って首をかしげた。良平の酒嫌いも相変わらずだったのである。
第12話
青ペン、赤ペン、白ペンと呼ばれる赤線に良平が出したパンパン屋には東京から素っ裸同然の女が流れてきた。着ているものでまともなのは下ばきだけという姿。彼女たちが着る着物から腰巻、帯、これらを古着屋から買ってきて着せるのもあきの仕事だった。
「おかみさん、それじゃ旦那の道楽に手を貸すことになりゃしないだかね」
久子はアイロンの手を休めることなくあきに対してそう言った。
「道楽ったって、家ん中持ち込んでくる道楽じゃないから」
あきの言葉は尻すぼみになった。さすがに「いいだよ」とは続けられなかった。もし恵旅館の切り盛りが大変でなかったら、あきは嫉妬の炎で身を焦がしていたかもしれない。さいわい亭主の道楽にかまけていられるほど暇ではなかった。あきの腹はすでに臨月に達していた。
数日後、あきは朝早く起きてかまどで湯を沸かしていた。その物音に目を覚まして久子が起きて行くとあきがタライに湯を張っていた。
「これからワタシャ子どもを産むからね」
あきはこともなげにそういうと自分の部屋に入って行った。
「旦那さんは?」
お産婆さんはとは聞かずに久子はそう言った。
「でかけてるよ」
あきは平然としていた。
久子はどうしていいかわからず一人でおろおろしていた。結婚生活の経験があるといってもわずか一カ月半。当然お産の経験はない。ノンちゃん、ユキちゃんを起こしに行こうと思ったが年上の自分でさえなすすべがないのだから無駄なことと覚った。
そのうち赤ん坊の泣き声がしたかと思うと部屋からあきが出てきて自分で産湯をつかいはじめた。久子は呆気にとられた。お産てこんな簡単なものかとわが目を疑った。
久子はむかし中国の関羽が馬良を相手に碁を打ちながら平然として名医華陀の肘の手術を受けたという三国志の話を思い出した。その手術の凄惨さに名医華陀でさえ額に脂汗を浮かべ、それを見ている侍臣のほうが真っ青になって顔をそむけてしまったというくだりである。久子の目には、あきがその関羽に匹敵する女偉丈夫にみえてきた。
久子は勝手でおでんやおしんこなどつくってあきの膳におすそ分けした。すると決まって翌日のお膳にあきのほうから何かしらお返しのおかずがそっと添えられてあった。
久子はこの家へ来てよかったと思った。
あきが町の婦人会の集まりに出て行くと旅館のおかみが口を揃えてこう言った。
「おたくの女中さんずいぶん居つくだねえ。ウチじゃあまた行っちゃったあ」
「他人だから、月給やってるから、といってそういうことじゃむずかしいよ。かといっておだてりゃいいってもんじゃないし、やっぱり感謝して使わなきゃ駄目だぜ」
「そうかねえ」
あきの言葉を聞いて他の旅館のおかみたちは溜息をついた。感謝するとはいってもなにせ相手のあること、言うは易く行うに難いことをよく知っているからだった。
「おかみさん、それじゃ旦那の道楽に手を貸すことになりゃしないだかね」
久子はアイロンの手を休めることなくあきに対してそう言った。
「道楽ったって、家ん中持ち込んでくる道楽じゃないから」
あきの言葉は尻すぼみになった。さすがに「いいだよ」とは続けられなかった。もし恵旅館の切り盛りが大変でなかったら、あきは嫉妬の炎で身を焦がしていたかもしれない。さいわい亭主の道楽にかまけていられるほど暇ではなかった。あきの腹はすでに臨月に達していた。
数日後、あきは朝早く起きてかまどで湯を沸かしていた。その物音に目を覚まして久子が起きて行くとあきがタライに湯を張っていた。
「これからワタシャ子どもを産むからね」
あきはこともなげにそういうと自分の部屋に入って行った。
「旦那さんは?」
お産婆さんはとは聞かずに久子はそう言った。
「でかけてるよ」
あきは平然としていた。
久子はどうしていいかわからず一人でおろおろしていた。結婚生活の経験があるといってもわずか一カ月半。当然お産の経験はない。ノンちゃん、ユキちゃんを起こしに行こうと思ったが年上の自分でさえなすすべがないのだから無駄なことと覚った。
そのうち赤ん坊の泣き声がしたかと思うと部屋からあきが出てきて自分で産湯をつかいはじめた。久子は呆気にとられた。お産てこんな簡単なものかとわが目を疑った。
久子はむかし中国の関羽が馬良を相手に碁を打ちながら平然として名医華陀の肘の手術を受けたという三国志の話を思い出した。その手術の凄惨さに名医華陀でさえ額に脂汗を浮かべ、それを見ている侍臣のほうが真っ青になって顔をそむけてしまったというくだりである。久子の目には、あきがその関羽に匹敵する女偉丈夫にみえてきた。
久子は勝手でおでんやおしんこなどつくってあきの膳におすそ分けした。すると決まって翌日のお膳にあきのほうから何かしらお返しのおかずがそっと添えられてあった。
久子はこの家へ来てよかったと思った。
あきが町の婦人会の集まりに出て行くと旅館のおかみが口を揃えてこう言った。
「おたくの女中さんずいぶん居つくだねえ。ウチじゃあまた行っちゃったあ」
「他人だから、月給やってるから、といってそういうことじゃむずかしいよ。かといっておだてりゃいいってもんじゃないし、やっぱり感謝して使わなきゃ駄目だぜ」
「そうかねえ」
あきの言葉を聞いて他の旅館のおかみたちは溜息をついた。感謝するとはいってもなにせ相手のあること、言うは易く行うに難いことをよく知っているからだった。
第13話
芸者ふさこが湯河原へ来たのは昭和三十二年九月一日のこと。この年の四月売春禁止法が実施され青ペン、赤ペン、白ペン、新世界などの赤線が大揺れに揺れているときのことだった。猶予期間の切れる来年四月一日には湯河原名物赤線の灯もいよいよ消えるというその最後のまたたきが、ふさこの目にはこよなく美しく見えた。
芸者が身を置く花柳界と赤線の間には明瞭に一線が引かれていたが、地の利からいえば互いに無縁ではありえなかった。宴席にはパンパンが酌に出ることもあったし、ふさこたち芸者衆が客を赤線に案内して行って「じゃあね、おあとはよろしく」と引き渡して帰ることもあった。
その赤線の灯もあくる年の四月完全に消えた。それからというもの座敷を終えて帰る夜道で、ふさこはよく男に抱きつかれた。赤線の灯は消えても一度火のついた男たちの欲情の火はなかなか冷めないようであった。
「赤線がなくて困るのは芸者も同じよ」
ふさこはあきにそう言ってこぼした。座敷が乱れて困るというのが芸者衆の一致した感想だった。
当時の芸者は百人を越す程度の数で古株は昭和二十三、四年頃から湯河原に来た姐さんがたである。年齢も出身地も本当のことをいわないのが芸者衆の常だが、古株は小田原の宮小路あたりから移った芸者であった。栄家の松栄などがその流れである。
三味も謡も習った古参の芸者に比べふさこは不器用で三味も謡もよくはしなかった。あきがいくら手ほどきをしても覚えようとしない。
「いいのよ、おかみさん。あたしゃこの社会に面白半分で入ったんだから」
そんなことを言っていて座敷に出ると「ハイヨーあたしのラバさんだよッ」と一枚ずつ脱いでいって裸になると扇子二本で前を交互に隠して客を喜ばせていた。芸としては上品ではなかったが、客を遊ばせるのはうまかった。座敷のにぎやかしには重宝した。
客が酔っ払ってクダを巻いても嫌がらずになだめたし、時間かまわずに居てくれてそれでいてあらかじめ決まった玉代しか取らなかった。そういう意味では毛並の変わった芸者といえた。
「なんだいあの顔のまずい芸者、ここ来るといつもいるな」
目時浅太郎はあきをつかまえてそう言った。恵旅館はいまや鳶とテキ屋の定宿のようになっていた。
客がとくに芸者を指名しない限りどこの置屋に声をかけどの芸者を呼ぶかは旅館側の裁量である。いっぺん入れて客のウケの悪かったような芸者はまず声をかけない。芸者は芸が売物だがある面では人気商売である。ふさこはあきのウケがよかった。これはと思うととことん面倒を見るのがあきの性分だった。
浅太郎も恵旅館へ来るとふさこを呼んだ。はじめて呼ぶのを初回、二度目はウラを返すといい、三度目からおなじみといってはじめてお客さんと呼ばれるようになる。浅太郎をはじめ鳶の頭連中は軒並みふさこのなじみになった。頭連中の座敷になるとふさこは時間まで芸者をつとめ、いったん帰ると着替えて戻り朝までバクチの世話をやいて一緒に遊んだ。
芸者が身を置く花柳界と赤線の間には明瞭に一線が引かれていたが、地の利からいえば互いに無縁ではありえなかった。宴席にはパンパンが酌に出ることもあったし、ふさこたち芸者衆が客を赤線に案内して行って「じゃあね、おあとはよろしく」と引き渡して帰ることもあった。
その赤線の灯もあくる年の四月完全に消えた。それからというもの座敷を終えて帰る夜道で、ふさこはよく男に抱きつかれた。赤線の灯は消えても一度火のついた男たちの欲情の火はなかなか冷めないようであった。
「赤線がなくて困るのは芸者も同じよ」
ふさこはあきにそう言ってこぼした。座敷が乱れて困るというのが芸者衆の一致した感想だった。
当時の芸者は百人を越す程度の数で古株は昭和二十三、四年頃から湯河原に来た姐さんがたである。年齢も出身地も本当のことをいわないのが芸者衆の常だが、古株は小田原の宮小路あたりから移った芸者であった。栄家の松栄などがその流れである。
三味も謡も習った古参の芸者に比べふさこは不器用で三味も謡もよくはしなかった。あきがいくら手ほどきをしても覚えようとしない。
「いいのよ、おかみさん。あたしゃこの社会に面白半分で入ったんだから」
そんなことを言っていて座敷に出ると「ハイヨーあたしのラバさんだよッ」と一枚ずつ脱いでいって裸になると扇子二本で前を交互に隠して客を喜ばせていた。芸としては上品ではなかったが、客を遊ばせるのはうまかった。座敷のにぎやかしには重宝した。
客が酔っ払ってクダを巻いても嫌がらずになだめたし、時間かまわずに居てくれてそれでいてあらかじめ決まった玉代しか取らなかった。そういう意味では毛並の変わった芸者といえた。
「なんだいあの顔のまずい芸者、ここ来るといつもいるな」
目時浅太郎はあきをつかまえてそう言った。恵旅館はいまや鳶とテキ屋の定宿のようになっていた。
客がとくに芸者を指名しない限りどこの置屋に声をかけどの芸者を呼ぶかは旅館側の裁量である。いっぺん入れて客のウケの悪かったような芸者はまず声をかけない。芸者は芸が売物だがある面では人気商売である。ふさこはあきのウケがよかった。これはと思うととことん面倒を見るのがあきの性分だった。
浅太郎も恵旅館へ来るとふさこを呼んだ。はじめて呼ぶのを初回、二度目はウラを返すといい、三度目からおなじみといってはじめてお客さんと呼ばれるようになる。浅太郎をはじめ鳶の頭連中は軒並みふさこのなじみになった。頭連中の座敷になるとふさこは時間まで芸者をつとめ、いったん帰ると着替えて戻り朝までバクチの世話をやいて一緒に遊んだ。
第14話
ふさこが来た当座に比べると湯河原は逆に落ち着いた湯治場の雰囲気を取り戻していた。不夜城のような賑いがうそのように思われた。その間に恵旅館は鉄筋の建物を二棟新築し、その名を恵ホテルと変えたことをみてもわかるように全体として客はふえたはずだ。が、熱海のような歓楽郷としての賑いはかげをひそめていた。
ふさこはこの湯河原に根を生やしたように居座っていつしか古参に数えられるようになっていた。
ある座敷にふさこは若い芸者を三人ほど連れて出た。客は千葉の肉屋の一行十二人ほど。
「あの社長は口が悪いからね。気をつけてね」
その旅館のおかみに念を押されていた。
「オイ!」と早速来た。ふさこはすかさず返事を返した。「なんだよ!」
社長は呆気にとられた顔をした。
「おそろしく元気のいいのが来たな。オイ、どうだい。若いのとコレできるか」
ふさこは社長の手を見た。人差指と中指の間から赤い親指の頭がのぞいている。
「できないよ」
「おめえもハッキリ言うなあ」
「ハッキリ言わなきゃなにごともハッキリしないじゃないのよ」
「おんめえ俺と気性そっくりだな。ズケズケずいぶんハッキリ物をいうじゃねえか」
「そりゃそうだろ。わたしゃ頭(かしら)の座敷出てるからね。クニャクニャなんかしてたらついていけないよ」
ふさこはいつもこんなふうな江戸っ子を女にしたような口のきき方をした。それで客と衝突するかというとそうではない。
売れっ子の若い芸者を連れて大きな座敷に出たときのことである。二次会に料亭へ流れたその席で、売れっ子の若い芸者が話のはずみから「さいきんの客は遊び方を知らない」とつい口走った。
相手の客が顔を真っ赤にして怒鳴った。
「ナニオッ、金で買われた芸者の分際で生意気な口をきくな!」
ふさこはすっとんで行って客に頭を下げた。
「スイマセン。ごめんなさい」
「姐さんが悪いんじゃないよ。あいつが悪いんだよ」
機先を制されて客は怒りの継穂を失った。
「若いこのそそうは一緒に入ったあたしのそそうですから、あいスイマセンごめんなさい」
なんどもふさこに謝られては客は気分を取り直して飲み始めた。
ふさこは分浜乃家の浜太郎とは「カーといえばツー」という仲である。閉鎖的なこの世界では本音で話す場というものがない。座敷の帰りふさこはよく酔った浜太郎を抱えて帰った。浜太郎は座敷のうっぷんばらしにふさこにからむ。売れっこの若い芸者に限らず「さいきんの客は遊び方を知らない」というのはどの芸者も感じていること。同じように客を遊ばせられる芸者も少なくなってきていた。親しい相手だとついそうしたことへの不満が口をついて出る。ここでもふさこは聞き役にまわった。
「ごめんね。あんたに言いたいこと言って。ごめんね」
家へ帰るとすぐ浜太郎から電話がかかってきた。
ふさこはこの湯河原に根を生やしたように居座っていつしか古参に数えられるようになっていた。
ある座敷にふさこは若い芸者を三人ほど連れて出た。客は千葉の肉屋の一行十二人ほど。
「あの社長は口が悪いからね。気をつけてね」
その旅館のおかみに念を押されていた。
「オイ!」と早速来た。ふさこはすかさず返事を返した。「なんだよ!」
社長は呆気にとられた顔をした。
「おそろしく元気のいいのが来たな。オイ、どうだい。若いのとコレできるか」
ふさこは社長の手を見た。人差指と中指の間から赤い親指の頭がのぞいている。
「できないよ」
「おめえもハッキリ言うなあ」
「ハッキリ言わなきゃなにごともハッキリしないじゃないのよ」
「おんめえ俺と気性そっくりだな。ズケズケずいぶんハッキリ物をいうじゃねえか」
「そりゃそうだろ。わたしゃ頭(かしら)の座敷出てるからね。クニャクニャなんかしてたらついていけないよ」
ふさこはいつもこんなふうな江戸っ子を女にしたような口のきき方をした。それで客と衝突するかというとそうではない。
売れっ子の若い芸者を連れて大きな座敷に出たときのことである。二次会に料亭へ流れたその席で、売れっ子の若い芸者が話のはずみから「さいきんの客は遊び方を知らない」とつい口走った。
相手の客が顔を真っ赤にして怒鳴った。
「ナニオッ、金で買われた芸者の分際で生意気な口をきくな!」
ふさこはすっとんで行って客に頭を下げた。
「スイマセン。ごめんなさい」
「姐さんが悪いんじゃないよ。あいつが悪いんだよ」
機先を制されて客は怒りの継穂を失った。
「若いこのそそうは一緒に入ったあたしのそそうですから、あいスイマセンごめんなさい」
なんどもふさこに謝られては客は気分を取り直して飲み始めた。
ふさこは分浜乃家の浜太郎とは「カーといえばツー」という仲である。閉鎖的なこの世界では本音で話す場というものがない。座敷の帰りふさこはよく酔った浜太郎を抱えて帰った。浜太郎は座敷のうっぷんばらしにふさこにからむ。売れっこの若い芸者に限らず「さいきんの客は遊び方を知らない」というのはどの芸者も感じていること。同じように客を遊ばせられる芸者も少なくなってきていた。親しい相手だとついそうしたことへの不満が口をついて出る。ここでもふさこは聞き役にまわった。
「ごめんね。あんたに言いたいこと言って。ごめんね」
家へ帰るとすぐ浜太郎から電話がかかってきた。
第15話
愚痴をいう、からむといっても仕事上のウサにすぎない。芸者をやっていて芸者稼業が大変だなどと思っている芸者はひとりもいない。さいきんは金を稼ぐ目的で芸者になる若い女がふえてはいるがそれも嫌でなるわけではない。歌って踊ってハシャいで座をにぎやかせてそれでくらしてゆけるのだから金を払って同じことをする客と比べれば月とスッポンである。さいきんの客は遊びを知らなくなったといっても、それは夫婦で来て芸者を三人もあげて奥さんを楽しませ自分はそれを見て喜ぶような粋な客が少なくなっただけである。ご祝儀をくれる客が減ったといってもそれは唯単に時代の流れ。玉代を払えば客は客である。客に感謝するのを忘れないようにしようとふさこが自分に言いきかせるようになったのも恵ホテルのおかみのおかげだった。
ふさこは湯河原のというよりも恵ホテルのといってもよいほどあきに目をかけてもらっていた。芸者の生活はお座敷からかかる声にかかっていた。どんなによい芸を持っていてもお声がかからなければ干乾しになってしまう。三味線も弾けないふさこがタチひとつで二十八年も湯河原で芸者を続けてこられたのはあきの存在なくしては考えられなかった。ふさこは恵ホテルの座敷では女中の代わりもやった。
「きょうはふさこ姐さん入ってる?」
「の、ようよ」
「じゃふさこ姐さんにまかせとこうよ」
チーちゃんこと久子もノンちゃんもユキちゃんもいまや恵ホテルの最古参女中になっていた。ふさこはそうした女中からも信任が厚かった。
ある日、恵ホテルに一人の上客が現れた。通しと呼ばれる呼びこみが連れてきた客である。入ってくるなりみんなの前でキッチリ束ねた一万円札の札束を見せ、再び風呂敷に包んでフロントに預けた。
芸者を四人、五人とあげてのドンチャン騒ぎが始まった。むろんふさこも呼ばれた。芸者といわず女中といわず飲めや食えやの大盤振舞い。さすがにあきは不安を覚えてきた。どうもうさん臭い。
そう思うが客商売では誰何するわけにいかない。女中に聞くと景気よく飲み食いするわりにはチップもくれないという。いよいよクサイ。
まごまごするうちに客は「これから熱海行く」といって芸者を引き連れて行ってしまった。
「あすの昼には帰るから」
大金を預けてあるんだ文句あるまいといわんばかりである。
「番頭さん、お札見せてよ」
「駄目ですよ、おかみさん。そんなことしたらお客さんに叱られますよ」
番頭に拒まれてあきは唇を噛んだ。
あくる朝、芸者だけ熱海から帰ってきた。さてこそと風呂敷を解いて札束をバラしてみると上と下の札だけが本物で後はニセモノだった。あききはその二万円だけで客に飲み食いさせた挙句芸者の玉代まで払わなければならないのである。
「おかみさん、あたしは玉代いいですから」
「そうはいかないよ」
あきとふさこは押し問答をした。結局、当日来た芸者の中でふさこだけ玉代を半分泣くことで話がついた。気は心とあきはふさこの気持ちを快く受けることにした。
ふさこは湯河原のというよりも恵ホテルのといってもよいほどあきに目をかけてもらっていた。芸者の生活はお座敷からかかる声にかかっていた。どんなによい芸を持っていてもお声がかからなければ干乾しになってしまう。三味線も弾けないふさこがタチひとつで二十八年も湯河原で芸者を続けてこられたのはあきの存在なくしては考えられなかった。ふさこは恵ホテルの座敷では女中の代わりもやった。
「きょうはふさこ姐さん入ってる?」
「の、ようよ」
「じゃふさこ姐さんにまかせとこうよ」
チーちゃんこと久子もノンちゃんもユキちゃんもいまや恵ホテルの最古参女中になっていた。ふさこはそうした女中からも信任が厚かった。
ある日、恵ホテルに一人の上客が現れた。通しと呼ばれる呼びこみが連れてきた客である。入ってくるなりみんなの前でキッチリ束ねた一万円札の札束を見せ、再び風呂敷に包んでフロントに預けた。
芸者を四人、五人とあげてのドンチャン騒ぎが始まった。むろんふさこも呼ばれた。芸者といわず女中といわず飲めや食えやの大盤振舞い。さすがにあきは不安を覚えてきた。どうもうさん臭い。
そう思うが客商売では誰何するわけにいかない。女中に聞くと景気よく飲み食いするわりにはチップもくれないという。いよいよクサイ。
まごまごするうちに客は「これから熱海行く」といって芸者を引き連れて行ってしまった。
「あすの昼には帰るから」
大金を預けてあるんだ文句あるまいといわんばかりである。
「番頭さん、お札見せてよ」
「駄目ですよ、おかみさん。そんなことしたらお客さんに叱られますよ」
番頭に拒まれてあきは唇を噛んだ。
あくる朝、芸者だけ熱海から帰ってきた。さてこそと風呂敷を解いて札束をバラしてみると上と下の札だけが本物で後はニセモノだった。あききはその二万円だけで客に飲み食いさせた挙句芸者の玉代まで払わなければならないのである。
「おかみさん、あたしは玉代いいですから」
「そうはいかないよ」
あきとふさこは押し問答をした。結局、当日来た芸者の中でふさこだけ玉代を半分泣くことで話がついた。気は心とあきはふさこの気持ちを快く受けることにした。
第16話
結果の成否を考えればいまおのれがどうあるべきか、何をなすべきかは自からわかるというのが室伏良平の哲学だ。恵旅館が恵ホテルになり木造の建物の前後に鉄筋造りのホテルが二棟も建ったのには、良平の存在と働きが欠かせない。亭主だからといって決してあきの先には出ず良平は裏方に徹した。旅館の切り盛りはあきのほうが得手とみてあとに引っ込んだのである。が、自ら選んだ立場とはいえ気持ちとしては平静ではいられなかった。あきの働きに寄りかかっていたのでは対世間的に自分の立場というものが弱くなる。匂いを嗅ぐのも嫌だというほど酒が嫌いなこともあったが、良平が朝未明に家を出て帰りが十時、十一時になるまで旅行代理店まわりに精を出し始めたのはそのためだ。
ある日のこと、目時浅太郎が国内旅行社という代理店で伊勢参りの手配を頼んでいると小柄な男が振り分けにした荷を肩にかついで「湯河原の恵ホテルです」と言って入ってきた。見れば恵ホテルの半天を着ている。
アレレと思って浅太郎は良平を見た。
「番頭さん、しばらくだね」
「あいすみません、あちこちに足をのばしておりますんでつい間遠になりました。」
旅行者の社員とこんなあいさつを交わしている。
恵ホテルの番頭なら浅太郎もよく知っている。知ってはいるが良平ではない。
「アタシャ番頭なのでいますぐここで決断はしかねます。帰ったら主人によく相談してみます」
社員とやりとりしたあとぬけぬけとした顔で良平は言った。浅太郎はそのやりとりを見ていてさてはこれが評判のあきの亭主なのかと理解がいった。
こんなふうにして日本国中まわってやがんのか。芋虫みてえな格好して大したヤローだぜ。
舌を巻いて浅太郎はマジマジ良平の顔を見た。
良平がいう相談する主人とはあきのことである。自分の心の中であきを主人と呼ぶことで対抗心を燃やし、良平はともすると客寄せ行脚がおっくうになる気持ちを奮い立たせた。裏方に徹したからといってあきにシャッポを脱いだわけではない。
客が来てはじめてあきの働きが生きる。
その自負心がかえって良平に社長番頭の道を選ばせたのだともいえた。
朝、客が起きる前にホテルの玄関先を掃除するのも良平の日課だった。
「番頭、新聞持って来い」
「ヘイ」
たまたま早起きした客に用事を言いつけられても良平は決して「自分は社長でござい」というような顔はしなかった。
だれがみてもあきが表で良平が裏に見えた。表と裏がぴったり一致して世間とは表と裏は逆だが仲のよい夫婦に見えた。まわりの者もノミの夫婦とみていた。
が、このノミの夫婦は決してそんな生やさしいものではなかった。商売の世界では客の前で「ヘイヘイ」とへりくだっている良平も、一歩家庭の中へ足を踏み入れるとたちまちわからずやの一徹居士に変身した。
ある日のこと、目時浅太郎が国内旅行社という代理店で伊勢参りの手配を頼んでいると小柄な男が振り分けにした荷を肩にかついで「湯河原の恵ホテルです」と言って入ってきた。見れば恵ホテルの半天を着ている。
アレレと思って浅太郎は良平を見た。
「番頭さん、しばらくだね」
「あいすみません、あちこちに足をのばしておりますんでつい間遠になりました。」
旅行者の社員とこんなあいさつを交わしている。
恵ホテルの番頭なら浅太郎もよく知っている。知ってはいるが良平ではない。
「アタシャ番頭なのでいますぐここで決断はしかねます。帰ったら主人によく相談してみます」
社員とやりとりしたあとぬけぬけとした顔で良平は言った。浅太郎はそのやりとりを見ていてさてはこれが評判のあきの亭主なのかと理解がいった。
こんなふうにして日本国中まわってやがんのか。芋虫みてえな格好して大したヤローだぜ。
舌を巻いて浅太郎はマジマジ良平の顔を見た。
良平がいう相談する主人とはあきのことである。自分の心の中であきを主人と呼ぶことで対抗心を燃やし、良平はともすると客寄せ行脚がおっくうになる気持ちを奮い立たせた。裏方に徹したからといってあきにシャッポを脱いだわけではない。
客が来てはじめてあきの働きが生きる。
その自負心がかえって良平に社長番頭の道を選ばせたのだともいえた。
朝、客が起きる前にホテルの玄関先を掃除するのも良平の日課だった。
「番頭、新聞持って来い」
「ヘイ」
たまたま早起きした客に用事を言いつけられても良平は決して「自分は社長でござい」というような顔はしなかった。
だれがみてもあきが表で良平が裏に見えた。表と裏がぴったり一致して世間とは表と裏は逆だが仲のよい夫婦に見えた。まわりの者もノミの夫婦とみていた。
が、このノミの夫婦は決してそんな生やさしいものではなかった。商売の世界では客の前で「ヘイヘイ」とへりくだっている良平も、一歩家庭の中へ足を踏み入れるとたちまちわからずやの一徹居士に変身した。
第17話
部屋に飾る花はすべて良平が山から摘んできて活けていた。部屋が四十でも五十でもすべて自分でやらないと気がすまない性分なのである。その野の花がさいきんは絵に変わった。変わったのはよいがときにはカレンダーの絵が飾られたりすることがある。額縁も襖の桟を使った手造りの代物であった。
「オヤジ、みっともないからやめてくれよ」
大きくなった息子たちは反対してはずして歩いた。はずした絵を天井裏に隠す。ところが良平は根気よく家探ししてとうとう見つけ出してきてまた部屋という部屋にカレンダーの絵をかけて歩いた。
それをまたさらに息子たちがはずして歩く。イタチごっこだ。
こんどはうっちゃれ!
隠すと良平が探し出すのでとうとう息子たちは業を煮やして捨ててしまった。
玄関を直したときも悶着が起きた。
「先に敷いちゃっちゃ駄目だよ。壁だの天井だの内装が終えたあとで敷くんだよ」
内装工事がまだすまないうちに良平がじゅうたんを敷くと言い出したのである。工事の途中で敷けばせっかくのじゅうたんが汚れてしまう。
「いいじゃあねえか、汚さなきゃ」
良平は事もなげに言い放った。
「そりゃ汚さなきゃいいんだけど、工事する人がやりにくくなっちゃうじゃないか」
息子ばかりか帳場もこぞって反対した。が、良平は耳をかさない。
「絶対にやる!」
とうとうだれもいないときに業者を呼んでじゅうたんを入れさせてしまった。
良平は一事が万事こうだった。とにかく自分のいうままで他人と妥協することは絶対にしない。そんなこんなで室伏家では父親と息子の言い争いが絶えず行われてきた。あきの目には道理を振りかざす息子の説得がまったく無駄な努力と映る。言うだけ無駄ということはあき自身体験として身に染みているからである。 そのたびに、
「言うじゃねえよ」
あきは息子の尻をつねって顔をしかめた。
「よくあんなオヤジと何十年もいたもんだねえ」
長男の蔵雄はそういってボヤいた。
何十年と聞いてあきはふっと吐息をついた。といっても夫婦の来し方行く末を想ったわけではない。家族といっても、いまでは実の家族よりもはじめの頃から労苦をともにしてきた久子やノンちゃん、ユキちゃんのほうが身内の家族という気がしていた。ノンちゃんに亭主の世話をし、三人ともに駅の近くへ男でも建てられないような立派な家を持たせることができた。もちろんそれは三人の努力の賜。三人の努力の賜ではあるがあきにはそれがうれしい。娘を立派に育てあげた母親の満足感ともいえようか。
あきの瞼に久子の家の建前の光景が浮かんだ。
農家へ嫁に行った久子の上の姉はトラックに餅を山と積んできてバラまいた。沼津の水産加工屋へ嫁に行った下の姉は魚やカニをわんさと運びこんで近所の人を仰天させた。姉たちはみんな幸せな暮らしをしていた。ひとり久子だけが……そんな想いと励ましが久子の胸にもあきの胸にもびんびんひびいてきた。
そのときあきは勝気な久子が涙を流す姿をはじめて見た。
「オヤジ、みっともないからやめてくれよ」
大きくなった息子たちは反対してはずして歩いた。はずした絵を天井裏に隠す。ところが良平は根気よく家探ししてとうとう見つけ出してきてまた部屋という部屋にカレンダーの絵をかけて歩いた。
それをまたさらに息子たちがはずして歩く。イタチごっこだ。
こんどはうっちゃれ!
隠すと良平が探し出すのでとうとう息子たちは業を煮やして捨ててしまった。
玄関を直したときも悶着が起きた。
「先に敷いちゃっちゃ駄目だよ。壁だの天井だの内装が終えたあとで敷くんだよ」
内装工事がまだすまないうちに良平がじゅうたんを敷くと言い出したのである。工事の途中で敷けばせっかくのじゅうたんが汚れてしまう。
「いいじゃあねえか、汚さなきゃ」
良平は事もなげに言い放った。
「そりゃ汚さなきゃいいんだけど、工事する人がやりにくくなっちゃうじゃないか」
息子ばかりか帳場もこぞって反対した。が、良平は耳をかさない。
「絶対にやる!」
とうとうだれもいないときに業者を呼んでじゅうたんを入れさせてしまった。
良平は一事が万事こうだった。とにかく自分のいうままで他人と妥協することは絶対にしない。そんなこんなで室伏家では父親と息子の言い争いが絶えず行われてきた。あきの目には道理を振りかざす息子の説得がまったく無駄な努力と映る。言うだけ無駄ということはあき自身体験として身に染みているからである。 そのたびに、
「言うじゃねえよ」
あきは息子の尻をつねって顔をしかめた。
「よくあんなオヤジと何十年もいたもんだねえ」
長男の蔵雄はそういってボヤいた。
何十年と聞いてあきはふっと吐息をついた。といっても夫婦の来し方行く末を想ったわけではない。家族といっても、いまでは実の家族よりもはじめの頃から労苦をともにしてきた久子やノンちゃん、ユキちゃんのほうが身内の家族という気がしていた。ノンちゃんに亭主の世話をし、三人ともに駅の近くへ男でも建てられないような立派な家を持たせることができた。もちろんそれは三人の努力の賜。三人の努力の賜ではあるがあきにはそれがうれしい。娘を立派に育てあげた母親の満足感ともいえようか。
あきの瞼に久子の家の建前の光景が浮かんだ。
農家へ嫁に行った久子の上の姉はトラックに餅を山と積んできてバラまいた。沼津の水産加工屋へ嫁に行った下の姉は魚やカニをわんさと運びこんで近所の人を仰天させた。姉たちはみんな幸せな暮らしをしていた。ひとり久子だけが……そんな想いと励ましが久子の胸にもあきの胸にもびんびんひびいてきた。
そのときあきは勝気な久子が涙を流す姿をはじめて見た。
第18話
久子の家の建前では目時浅太郎が鳶の仲間を大勢連れて来て木遣りをやった。
何事かと近所の人が驚くような立派な建前になった。
「辛抱は金、金、といいますけどね。三十五年……おかみさん、ここまでやってこられたのはみんなおかみさんのおかげです。感謝してます。三十五年といえば生まれた自分の家よかここのほうが長いんですものねえ」
建前を終えて帰ると久子は涙をかくすようにして一気にまくしたてた。
「三十五年ねえ」
あきも感慨深げにつぶやいた。
「猫なら化けて出るよ」
そばから浅太郎が茶化した。浅太郎もすでに七十に手の届くところに来ている。そういう浅太郎の目も赤く充血していた。
「三十五年だものね」
ノンちゃんもユキちゃんもほっと吐息をついた。浅太郎が吠えた。
「でも、みんないてよかったんだよな。俺たちだってあんな真似できないよ。地所買って家おっ建てて」
「そうね。だから家も出来るしね。おかみさんに叱られながらでもなんでもね」
「サッちゃんどうしてるかしら?」
ふとノンちゃんがつぶやいた。
サッちゃんというのは三人がまだ恵旅館に来たばかりの頃進駐軍のオンリーになるために親に連れ出された女中っこである。三人の今日があるだけにあきは胸がいたんだ。
「あんときはあっちのほうがコレになるだったもの。ウチにいるよか」
あきは言いわけともつかず指を丸めて言った。
「俺は失敗しちゃったと思ってるよ。チーちゃんと一緒になってりゃ苦労しなかった」
「そのかわりあたしが苦労しているわよ」
浅太郎は月に二回三回と来ては三、四日泊まるようになっていた。恵ホテルの人間は浅太郎を見てだれも「いらっしゃい」とはいわない。「お帰りなさい」というのが浅太郎に対するあいさつになっていた。浅太郎一人でもよい顧客だったが、浅太郎の枝葉となってやってくる客がまた恵ホテルにとっては大きかった。
あきは三十五年前の横っトビと小田原漁師の大立ちまわりを思い出した。広間で鳶と漁師が大喧嘩をしているとき、あきはままね館の脇で吹き出した温泉と湯けむりを見てピンコロとびはねていた。
あの頃はみんなまだ盛んだった。
湯が出たうれしさで鳶と漁師の喧嘩を警察沙汰にせず金も取らずにおさめて帰したが、あの日もし湯けむりが立たなかったらはたしてあんな絵に描いたような真似が出来たかどうか。目の前の浅太郎を見ていてあきは湯けむりが立つように目が曇るのを感じた。
その後、数年ぶりで小田原の元漁師たちがやって来た。いまでは漁師をやめて板前や料理屋のオヤジになっている。
「あのときのお客さん、ほら大喧嘩した……いまでもよく見えてますよ」
「ほお、そうかね。来てるだかね」
元漁師たちもなつかしそうに目を細めた。
何事かと近所の人が驚くような立派な建前になった。
「辛抱は金、金、といいますけどね。三十五年……おかみさん、ここまでやってこられたのはみんなおかみさんのおかげです。感謝してます。三十五年といえば生まれた自分の家よかここのほうが長いんですものねえ」
建前を終えて帰ると久子は涙をかくすようにして一気にまくしたてた。
「三十五年ねえ」
あきも感慨深げにつぶやいた。
「猫なら化けて出るよ」
そばから浅太郎が茶化した。浅太郎もすでに七十に手の届くところに来ている。そういう浅太郎の目も赤く充血していた。
「三十五年だものね」
ノンちゃんもユキちゃんもほっと吐息をついた。浅太郎が吠えた。
「でも、みんないてよかったんだよな。俺たちだってあんな真似できないよ。地所買って家おっ建てて」
「そうね。だから家も出来るしね。おかみさんに叱られながらでもなんでもね」
「サッちゃんどうしてるかしら?」
ふとノンちゃんがつぶやいた。
サッちゃんというのは三人がまだ恵旅館に来たばかりの頃進駐軍のオンリーになるために親に連れ出された女中っこである。三人の今日があるだけにあきは胸がいたんだ。
「あんときはあっちのほうがコレになるだったもの。ウチにいるよか」
あきは言いわけともつかず指を丸めて言った。
「俺は失敗しちゃったと思ってるよ。チーちゃんと一緒になってりゃ苦労しなかった」
「そのかわりあたしが苦労しているわよ」
浅太郎は月に二回三回と来ては三、四日泊まるようになっていた。恵ホテルの人間は浅太郎を見てだれも「いらっしゃい」とはいわない。「お帰りなさい」というのが浅太郎に対するあいさつになっていた。浅太郎一人でもよい顧客だったが、浅太郎の枝葉となってやってくる客がまた恵ホテルにとっては大きかった。
あきは三十五年前の横っトビと小田原漁師の大立ちまわりを思い出した。広間で鳶と漁師が大喧嘩をしているとき、あきはままね館の脇で吹き出した温泉と湯けむりを見てピンコロとびはねていた。
あの頃はみんなまだ盛んだった。
湯が出たうれしさで鳶と漁師の喧嘩を警察沙汰にせず金も取らずにおさめて帰したが、あの日もし湯けむりが立たなかったらはたしてあんな絵に描いたような真似が出来たかどうか。目の前の浅太郎を見ていてあきは湯けむりが立つように目が曇るのを感じた。
その後、数年ぶりで小田原の元漁師たちがやって来た。いまでは漁師をやめて板前や料理屋のオヤジになっている。
「あのときのお客さん、ほら大喧嘩した……いまでもよく見えてますよ」
「ほお、そうかね。来てるだかね」
元漁師たちもなつかしそうに目を細めた。
完